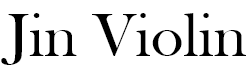バイオリンが映画音楽に使われることは大変多いようです。
あの美しい音色が、映画の背景や、登場人物の心情などを表現してくれて
映画をよりドラマティックに演出します。
そんなバイオリンの音色が際立つ、映画の名作をご紹介しましょう!
バイオリンがテーマの名作映画3作をご紹介!

屋根の上のバイオリン弾き
「屋根の上のバイオリン弾き」(英語原題:Fiddler on the Roof)は
1964年のアメリカのミュージカルです。
ショーレム・アレイヘムの短編小説「牛乳屋テヴィエ」が原作となっています。
テヴィエとその家族、そして帝国ロシア領となったシュテットルに暮らす
ユダヤ教徒の人生を描いた、ブロードウェイ史に輝く名作となっています。
~屋根の上のバイオリン弾きの名曲~
・「サンライズ・サンセット」・・・・主人公の長女の結婚式のシーンで歌われた曲で
親の心をしみじみと表した有名なナンバーです。
・「トラディション」・・・ユダヤ教徒の厳しい戒律を表した曲です。軽快で力強い
ナンバーになっています。ソロヴァイオリニストは
ユダヤ系のアイザック・スターンでした。
・「イフ・アイ・ワー・ア・リッチマン」・・・「もし私が金持ちなら」のくだりは、
英会話の仮定法によく使われているのを思い出しませんか?
「お金さえあったら、こんなに汗水たらして働かなくていいのに・・・
ヤハ ディダディダ ババババ ディダディダ」という部分がコミカルな曲になってます。
この「屋根の上のバイオリン弾き」のミュージカルは、日本でもロングヒットになっていて
1967年から1986年まで900回にわたり、森繁久彌が主役のテヴィエ役をつとめました。
その後、上條恒彦、西田敏行、市村正親へと引き継がれています。
昨年亡くなられた神田沙也加さんも、次女のホーデル役で市村版の舞台に立っていました。
「俺たちユダヤ人は皆屋根の上のバイオリン弾きみたいなものだ。
落ちて首の骨を折らないよう、気を付けながら愉快で素朴な調べを
かき鳴らそうとしているのだ」
「貧乏が恥でないことはわかっていますが、大した名誉でもありませんな」
ーテヴィエ

パガニーニ ~愛と狂気のバイオリニスト~
音楽史上もっとも有名である、イタリアのバイオリニスト、ヴォイスト、ギタリスト
そして作曲家である、「ニコロ・パガニーニ」の伝記映画です。
パガニーニは、そのあまりの超絶技巧の演奏スタイルから、
「あいつは魂を悪魔に売って、その代償にあの演奏テクニックを授かったのだ」と
信じられていたほどのヴァイオリンの名手でした。
しかし、彼の私生活は、ギャンブルと酒と女にまみれていた堕落したものでした。
美しい声を持つ女性シャーロットと出会い、彼の人生に変化が訪れますが・・・
映画では、パガニーニ役を本物のバイオリニストである、イケメンモデルでも有名な
デビッド・ギャレッドが熱演し、実際に演奏をしています。
劇中で5億円のストラディヴァリウスが奏でる曲は必聴ですよ!!
~映画「パバニーニ」の収録曲~
・「カプリース 第24番」・・・鬼才パガニーニが作曲した
一番有名な曲で「24のカプリース」の最後を飾る作品です。
・「ラ・カンパネラ」・・・「カンパネラ」というのはイタリア語で「鐘」を意味します。
これまたよく知られた曲ですね。
・「バイオリンとギターのためのソナタ 第12番 ホ短調 Op.3」
パガニーニはギターのための作品も多く残しています。
美しい調べにうっとりしてしまうことでしょう・
「パガニーニは二度繰り返さない。」(アンコールを求めた王に対して言った言葉)
「8歳になるころ、父の指導のもと、ソナタを一つ作曲した。」
「私にとって作曲は決して簡単なものではない。
芸術において大切なのは、多様さの中における完全な調和であり、
それを達成するのは非常に難しい」
ーニコロ・パガニーニ
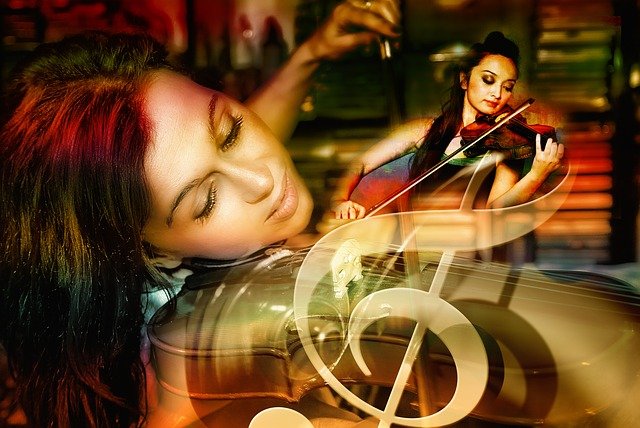
ミュージック・オブ・ハート
製作は1996年アメリカ。 実在した人物、音楽教師ロベルタと子どもたちの
13年にわたる交流を描いた感動作品です。
荒れ果てたスラム街で子どもたちにバイオリンを教えることで、
人種差別に苦しむ子どもたちに音楽のすばらしさを教え、社会をも変えていく
女音楽教師を演じるのは、かのアカデミー賞最多数女優、メリル・ストリープ。
ラストに流れるバッハの「二つのバイオリンのための協奏曲ニ短調」が流れるころには、
思わず立ち上がって、「ブラボー!」と拍手を送りたくなりますよ!
~映画「ミュージック・オブ・ハート」の収録曲~
・「ミュージック・オブ・マイ・ハート」・・・あのラテン系ポップ歌手
グロリアエステファンが主題歌を歌い、映画にも出演しています。
・「ナッシング・エルス」・・・スペインの大物歌手の息子、「フリオイグレシアスJr」
が美しいスパニッシュギターに合わせて情熱的に歌います。
バイオリンの映画ですが、全体的にラテン曲が多く、ノリノリの出来になっています!
「バイオリンを習うことは、人生において努力することによって、
何が可能になるか教えてくれる」
「音楽を楽しむのに、作曲家の肌の色が関係ある?」
「人は足だけで立っているのではないわ。心でも立つのよ。」
「子どもなら誰でもバイオリンを弾けるはず。」
ーロベルタ・ガスパーリ
いかがでしたか?
3つの映画はそれぞれ時代も表現も違いますが、言えることは
「バイオリンの音色がいかにドラマチックであるか」
ではないでしょうか?
そのシーンによって、楽しく、軽快であったり、
恐怖に満ちていたり、悲しみ涙があふれて胸が張り裂けそうになったり・・・
バイオリンの音色が、その映画を数倍も素晴らしいものに仕上げてくれる
魔法の楽器であることに、気づかされました。
そして、驚いたことに「ミュージック・オブ・ハート」のヴァイオリン教師役の
メリル・ストリープは、この映画のために猛特訓をして、映画の中のシーンで
実際に演奏をしているというのだから、いやはや大女優はすごいですよね!
映画は少し敷居が高く見えるバイオリンの世界を、身近に感じさせてくれて、
「自分も頑張って弾いてみたい!」という気持ちにさせてくれました。