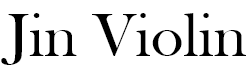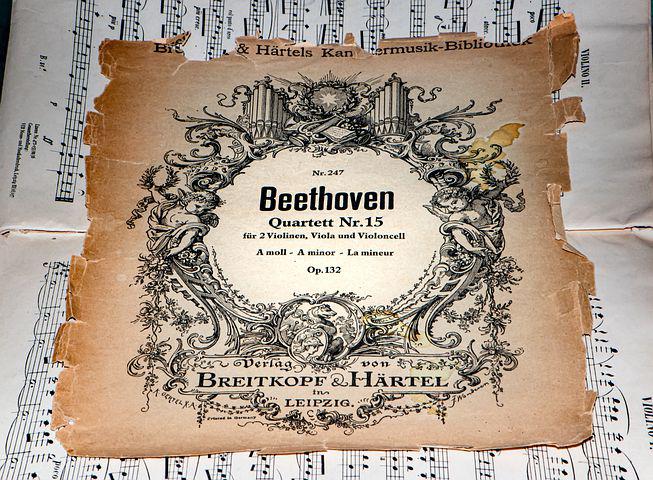
この世に数々の名曲を生み出した、音楽家の「ベートーベン」。
音楽演奏者やバイオリン演奏者であれば、誰もがベートーベンの曲に一度は憧れることでしょう。
今回は、ベートーベンが作曲したおすすめのバイオリン曲を紹介します。あわせてベートーベンの歴史やおすすめの練習曲も徹底解説します。
ベートーベンってどんな人物?意外と知らないベートーベンの歴史

ベートーベンは1770年にドイツで生まれ、ハイドンやモーツァルトなど有名な音楽家たちと共に、古典音楽を代表する人物です。
幼い頃から音楽に触れ、25歳という若さで初めてピアノ協奏曲を作曲したベートーベン。その後、難聴に悩まされながらも数多くの名曲を残し、今でもベートーベンの曲を一曲も知らないという人はいないと言っても過言ではありません。
死ぬまで作曲をしていたベートーベンの曲は、時代を超えて多くの音楽家たちから今も愛され続けています。
ベートーベンのおすすめバイオリン5選

ベートーベンが作曲した曲の数は非常に多く、どの曲を演奏すれば良いのかわからない人も少なくないはずです。
ここからは、ベートーベンのおすすめのバイオリン曲を5曲紹介します。
バイオリンと管楽器のためのロマンス第2番へ長調50
バイオリンと管楽器のためのロマンス第2番は、バイオリン独特の美しい音色と管楽器の優しい音色の組み合わせが印象的な一曲です。
「ロマンス」という名がぴったりの、ロマンチックで愛のある雰囲気の曲調が、長年多くの人の心を掴んでいます。
ヴァイオリン・ソナタ第5番へ長調作品24「春」
ソナタ第5番の「春」という作品は、1800年から1801年に作曲された特に有名な曲の一つです。
形式も和音の響きもまるで交響曲のようにダイナミックであり、ピアノと一緒に演奏することで、より美しさが増します。
ヘ長調で明るくさわやかな曲調は、「春」という名前がぴったりの一曲です。
ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調作品47「クロイツェル」
ソナタ第9番イ長調「クロイツェル」は、1802年から1803年にかけて作曲されたベートーベンの傑作作品です。
「クロイツェル」という名は、名ヴァイオリニストの名前からきているといわれています。緊張感のあるスリリングな曲調が特徴で、切ない恋物語を描いたストーリー性のあるこの曲は、聴く人を圧倒させます。
ロマンス第2番へ長調作品50
ロマンス第2番へ長調は、1798年に作曲されたヴァイオリンと管弦楽のための楽曲です。
ロマンス曲で有名な「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」や、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第20番」と同じく、感情的で甘い曲調が特徴です。
ゆったりした曲調で穏やかな雰囲気がバイオリンの音色の美しさを際立てる一曲です。
ヴァイオリン協奏曲二長調作品61
ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品は、ベートーベンが友人のために作曲した唯一のヴァイオリンのための協奏曲です。
ベートーベンはピアノの名手として有名ですが、彼は弦楽器が得意ではなかったという説があります。そのため、この曲は非常に貴重な作品であり、「ヴァイオリン協奏曲の王者」と呼ばれるほどです。
協奏曲らしい煌びやかさはなく、どちらかというと落ち着いた雰囲気が特徴です。
また、演奏の難易度が高いことでも有名で、見せ場もわかりにくい作品であることから、プロのバイオリン演奏者でも見事に演奏することは難しいといわれています。
ベートーベンは初心者には難易度が高い?

ベートーベンやモーツァルト、バッハなど有名な音楽家が作曲した曲は初心者には少し難しいと考えられます。
これらの曲に挑戦するためには、初心者のうちにしっかりと基礎を学んで練習し、目標の曲を目指して努力しましょう。
「どうしてもベートーベンの曲が弾きたい!」という場合は、番号が進むにつれ、難しくなるので前期の曲で練習してみるのをおすすめします。
独学では上達できない?バイオリン教室に通うメリット

ここまで、ベートーベンのおすすめ曲について紹介しました。さっそく練習してみたいと感じた方も多いのではないでしょうか。ここからは、バイオリンを学ぶ方法について解説していきます。
バイオリンを学ぶには、独学で学ぶ方法とバイオリン教室に通う方法の2通りの選択肢があります。
バイオリンは独学で学ぶことも可能ですが、バイオリン教室に通う方法を選ぶ方が一般的に多いです。なぜバイオリン教室に通う方が多いのでしょう。ここからは、バイオリン教室に通うメリットを紹介します。
メリット①正しいフォームを身につけられる
バイオリン教室ではバイオリンの持ち方や正しいフォームを学ぶことができます。
DVDやYouTubeでも学ぶことができますが、正しいフォームを維持したまま演奏するのは、非常に難しいとされています。
指導者が近くにいれば、間違っているところを指摘してくれるので、意識して練習ができ、身につくのも早いと考えられます。
メリット②わからないことをすぐに聞ける
バイオリンの練習は、初心者にとっては特に複雑であり、レベルが上がるにつれわからないことが増えてくると考えられます。
そのため、独学ではモチベーションの維持をするのは難しく、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
バイオリン教室は、元バイオリニストや経験者が指導者として教室を開いていることが多いため、悩みを一緒に解決してくれます。
いつでもわからないところを相談することができるので、楽しく続けられるでしょう。
メリット③自分のレベルに合った曲で練習できる
バイオリン初心者の中であれば、「どの曲から練習したら良いのかわからない」と悩んでしまう人も多くいるはず。
バイオリン教室では、指導者が自分のレベルに合った曲を選んで提案してくれます。そのため効率よく学ぶことができるので、独学より上達するのも早いと考えられます。
初心者におすすめの練習曲

少しでも憧れのベートーベンの曲に近づくために、ここからは初心者におすすめの練習曲を3曲紹介します。
どれも基礎から練習できる曲なので、ぜひ曲選びの参考にしてください。
きらきら星
きらきら星は、バイオリンを始めて最初に練習する曲としておすすめです。
基本的な音源にまんべんなく触れる練習ができ、短い曲なので1〜2週間程度で弾けるようになるでしょう。
また、少しレベルが上がると、変奏曲で何通りも練習することができます。
カエルの合唱
カエルの合唱は、曲の流れが音階になっており左指の動きがわかりやすくなります。
また、慣れ親しまれている曲なので覚えやすく、指慣らしの練習としてもよく使われます。
ユーモレスク
ユーモレスクは、チェコの作曲家による民族音楽のような曲です。
原曲は非常に難しい曲ですが、「スズキ・メソード教本」が初心者向けにアレンジ版を作曲したことから話題になりました。
軽快で楽しい曲調であることから、初心者からも人気の一曲です。
まとめ
今回はバイオリン初心者の方に向けて、天才音楽家「ベートーベン」のおすすめの曲や、彼に関する情報を紹介しました。
難聴になり音を聴くことができなくなっても、作曲をし続けた彼の傑作作品の数々は、長年多くの音楽演奏者から愛され続けています。
バイオリン初心者の方にとって、ベートーベンの曲は少し難易度の高いものが多いと考えられます。基礎をしっかり身につけ、憧れの曲に近づけるよう毎日練習に励むことが大切です。
演奏すればするほど、奥深く美しいのがベートーベンの曲の魅力です。